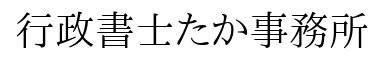限られた条件を満たした場合を除き、排出事業者(元請業者の事)以外の業者(下請けなど)が収集運搬するためには許可が必要です。
下請け業者が収集運搬業の許可なく運搬できる条件
- 新築・増築・解体工事ではない建設工事(維持修繕工事、瑕疵補修工事などであること)
- 請負金額(発注者の支払金額)が500万円以下の工事であること
- 特別管理産業廃棄物(飛散性のアスベストなど)が発生しないこと
- 1回に運搬する廃棄物は1㎥以下の容量であること
- 下請会社が受注した工事から発生した廃棄物のみが対象であること
- 建設現場と同一の県または隣接する県の、排出事業者が使用権限を持つ保管場所(排出事業者が委託契約した処理業者の処理施設も含む)へ運搬すること
- 運搬の途中で積替保管を行わないこと
- 保管場所からの廃棄物の処理に関しては、元請会社が排出事業者としての責任を果たすことができること
- 下請会社と交わす工事請負契約に、下請会社が運搬することを定めた内容を含むこと
- 運搬時には、上記契約書の写しを携帯すること
- 運搬時には、車輌の表示や書面の携帯などの運搬時の基準が適用されること
私としては「実質不可能なんじゃないかな?」と思います。
なのでここからはまず許可を取得するための要件、
その後、産業廃棄物の分類など詳しく知りたい方向けの解説をしていきたいと思います。
興味のある方は最後までお読みください。
要件① 講習会を受講し、修了証を手に入れる
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、「産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を有していること」が求められています。
受講が必要な方は、個人事業主の場合は事業主本人、法人の場合は法人代表者または役員です。
必ず1人は有効期間内の修了証を有していることが必要です。
講習会の詳細につきましては、
「日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」をご確認ください。
要件② 経理的基礎
建設業許可のように「500万以上」といった額が設定されているわけではありません。
しかし、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類などが求められ、債務超過や3期連続の赤字の場合には、追加書類として経営改善計画書(借入金返済計画書)の提出が求められます。
※法人を設立したばかりで決算期を迎えていない場合は、会社設立時の貸借対照表を添付すれば許可がとれます。
要件③ 運搬車両・運搬容器・駐車場があること
運搬車両は1台でも構いません。リースも可能。
ただし事業計画の内容と明らかに掛け離れている場合は事業計画の改善が必要です。
例えば、月100トンの瓦礫を運ぶのに軽トラ1台など。
石綿や水銀を含む産業廃棄物を収集運搬する場合には運搬容器が必要です。
駐車場の使用権限も必要です。(登記事項証明書・賃貸借契約書など)
要件④ 欠格要件に該当しないこと
欠格要件の対象となるのは
個人:個人事業主
法人:役員(相談役、顧問等を含む)・株主又は出資者
※発行済株式総数の5%以上の株主又は出資額の5%以上の出資をしている者
また、許可後に欠格事由に該当するに至った場合は許可の取り消し事由となります。
欠格要件
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法等の法律に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 次に掲げる罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
刑法第204条(傷害罪)、刑法第206条(現場助勢罪)、刑法第208条(暴行罪)、刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)、刑法第222条(脅迫罪)、刑法第247条(背任罪)など - 収集運搬業・処分業、浄化槽清掃業の許可の取消処分を受けてから5年を経過しない者
- 許可取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散又は廃業の届出を行った者で、その届出の日から5年を経過しない者
- 許可取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者で取消日(許可取消)又は届出の日(解散又は廃業)から5年を経過しない者
- 暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
以上が許可取得に必要な要件となります。面倒な手続きは行政書士に任せたいとお考えの方はこちらからお問合せください。
廃棄物の分類

廃棄物は上記のように分類されます。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物の種類を書こうと思いましたが、各行政庁・行政書士事務所などホームページに多数書かれているので、新潟県庁のリンクを貼っておきます。
新潟県庁:産業廃棄物の種類と具体例
特別管理産業廃棄物も同じページにあってわかりやすかったです。
産業廃棄物の種類の判断で注意すること
廃棄物がいつも単体なら困らないと思いますが必ずしもそうとは限りませんし、特別な処理をしなければならないものもあります。
- 混合物の存在(分離できない一体な物)
(1)普通物同士:構成する複数の品目として扱う
(2)普通物+特管物:同上=2種類の許可必要
(3)普通物+一般廃棄物:全体を産廃として扱う
- 普通物だが特別な処理が規定されているもの
(1)石綿含有産業廃棄物:石綿が飛散するおそれ
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものです。)
飛散しないようにするため石綿含有産業廃棄物を梱包し、又はシートで覆う等の措置や他の廃棄物と混合しないように仕切りを設ける等の措置をとって収集運搬することが必要です。
(2)水銀含有産業廃棄物:水銀が飛散・揮発するおそれ
水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等は、特管産廃に該当しませんが、処理基準が追加されました。排出事業者は、保管場所の掲示板に産業廃棄物の種類と、水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等が含まれる旨を示さなければなりません。また、処理を委託する際の新規契約や契約更新時に水銀使用製品産業廃棄物等が含まれている旨を契約書に記載しなければなりません。
(3)自動車等破砕物:有害物が溶出するおそれ
このように廃棄物処理法施行令等で産業廃棄物の処理基準が定められています。