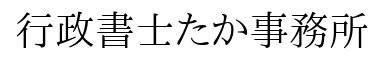「軽微な工事」とはどういうものですか?
「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が
①「建築一式工事」にあっては、1,500万円(税込)に満たない工事もしくは延べ面積が150㎡に満たない工事、
②「建築一式工事以外の建築工事」にあっては、500万円(税込)に満たない工事です。
なお、この請負代金の額の算定にあたっては、以下の点に注意が必要です。
ア)2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負金額の合計額
イ)注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
ウ)単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ)消費税及び地方消費税を含む額
(建設業法施行令第1条の2)
自宅に営業所を置いていますが、独立した営業所とみなされますか?
電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられている必要があります。また、玄関等には商号を表示してください。
申請してから許可を受けるまでにはどのくらい期間がかかるのですか?
知事許可の場合は、申請書を受け付けてから概ね30日程度かかります。大臣許可の場合は、申請書を受け付けてから概ね120日程度かかります。
※この期間には、形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間は含みません。また、適正な申請がなされていても、審査のため、申請者に必要な資料の提供等を求めてから申請者がその求めに応答するまでの期間は含みません。
専任技術者とはどんな人ですか?
請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。建設業の許可を受けるためには、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者を営業所ごとに置く必要があります。資格要件を満たす場合には、同一営業所内において2業種以上の建設業の専任技術者になることや、経営業務の管理責任者と兼ねることもできますが、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。
複数の業種を一人の専任技術者で担当できるますか?
必要な資格等をお持ちであれば、一人何業種の専任技術者になられても構いません。
建設業許可を受けた後、建設業者が行う必要な手続きは何がありますか?
①毎事業年度終了後、4か月以内に決算報告の提出が必要となります。
② 許可の有効期間は5年間となりますので、有効期間の満了の日の30日前までに更新申請が必要となります。
③商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30日以内に変更届の提出が必要となります。
④経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者が交替等をした場合は、14日以内に変更届の提出が必要となります。
決算報告は、決算書を提出すればよいのですか?
法令で決められた様式(法令様式)に書き直す必要があります。
決算報告は、更新のときにまとめて提出してはいけませんか?
決算報告は、毎事業年度終了後4ヶ月以内にご提出いただくことが、建設業法において義務付けられています。ご提出がないと、業種追加申請や更新申請はできません。提出を怠っていると、過去の決算期の納税証明書が取得できない場合があり、許可の継続が困難になるケースが見受けられます。また、ここ数年、建設業法施行規則の改正が複数回あり、決算期の時期によって使用する様式が異なります。まとめての作成は、かえって多大なる労力と時間がかかります。必ず事業年度ごとにご提出をお願いします。
1件の請負代金が500万円未満の場合、建設業許可を受けなくても工事がで きると聞きました。工事費は500万円未満なのですが、材料費を合わせると500万円 を超えてしまいます。その場合、建設業の許可は必要になるのでしょうか ?
材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、注文者が提供する材料費も合算して税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込み1500万円以上)となった場合は、建設業の許可が必要です。(建設業法施行令第1条の2)
建築一式工事業の許可を取得すれば、建築系工事であればどんな工事も請け負えるのですか?
建築一式工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500 万円以上の専門工事を単独で請け負うことは出来ません。土木一式工事も同様の扱いとなります。
業種追加で複数業種を申請する場合、手数料は業種ごとに計算するのですか?
手数料の金額は、業種の数ではなく、一般建設業・特定建設業の別で変わります。すべての業種がどちらか一方なら5万円、一般と特定にまたがる場合は10万円となります。
個人で許可を受けている父から長男が事業を引き継ぎました。建設業の許可も引き継ぐことができますか?
令和2年10月に事業承継に係る認可の手続きに関する規定が新設され、建設業の許可を引き継ぐことが可能となりました。
個人で許可を受けていましたが、法人化(法人成り)しました。個人の許可で引き続き営業することはできますか?
令和2年10月に事業承継に係る認可の手続きに関する規定が新設され、建設業の許可を引き継ぐことが可能となりました。個人事業主から法人に対して事業譲渡というかたちをとります。